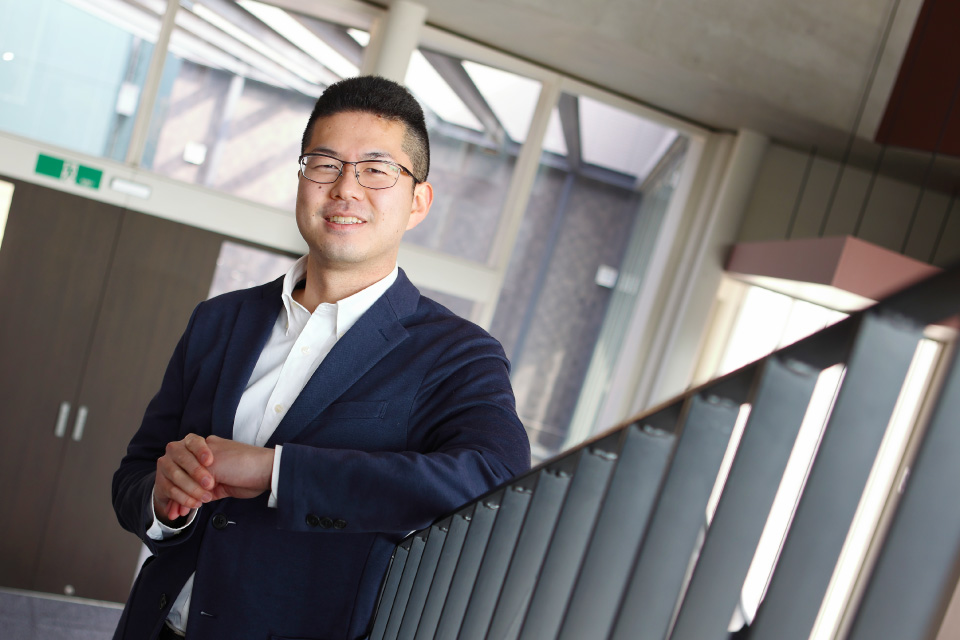情報数理学専攻
システム数理学講座
助教
岩崎 悟
Iwasaki Satoru
研究を変える、研究室を変わるというのは難しいことでしたか?
物理シミュレーションを必要とされる研究、つまり器具を使って実験しなければ進められない研究の場合、ある程度の研究歴のある異分子が、過去の研究成果やアプローチを持って転籍してくると、その人のために器具や実験計画を変更しなければならず、研究室の文化や運営に様々な影響が生じる場合があります。転籍する側も、自分の研究スタイルが維持可能かどうか、不安を感じることもあるでしょう。
しかし、情報数理学専攻は物理シミュレーションを必要とする実験はなく、対象をいかに数学で扱うか、モデルに落とし込むかの研究が主となります。先ほどお話したように、ペンと紙、PCがあれば成立します。その点では、新たなメンバーを受け入れても研究室に大きな影響はありません。転籍する側も同じく、自分のスタイルで研究を行うことができます。私も転籍に不安を感じたことはありませんでした。
もうひとつ私が安心できた理由は、阪大のIPSの研究室同士の横の繋がりの強さにあります。毎年、IPSの5つの研究室が全て参加して行う合同発表会があります。そこで各研究室のどのメンバーが、どのような研究に取り組んでいるかを知ることができます。各研究者の発表からは、刺激やヒントをもらえるので、私は毎年楽しみにしています。そういった機会を通して、各研究室の研究内容が分かっていたのも、転籍を決断する指針や安心材料になりました。
お互いの顔も研究も知っている同士なので、飲み会もよくあります。研究室内でホームパーティのように開催したり、近くの居酒屋に繰り出したり。学部生時代から、研究室の垣根を越えてよく集まり、交流していました。バカ話などもしますが、研究のことや研究者同士で人生相談をし合ったりもします。そんな会話の中で、研究に活かせるヒントや、もっと頑張ろうという刺激をもらえたりもします。日常の中にお互いを鼓舞し合える機会が多くあることも、私が健やかに研究を続けられている理由になっています。

研究の道に進むことを決断したのはいつですか?
幼稚園の頃から数字が好きで、算数も数学もずっと楽しみながら意欲的に取り組んできました。高校で物理を学び始めると、数式が現実世界の物理現象と関連してきて「微分方程式から世界を理解するのが面白い」と思うようになりました。そのまま理系を突き進み、大学は阪大の工学部に入学。1年生の頃は化学・生物も受講し、「細胞の動きにも微分方程式が応用できる!」と、数学で世界の多様な現象に寄りそえることにますます興味を持つようになりました。
大学院に進学し、尊敬できる恩師に出会えたこと、そして『大阪大学 ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラム※』に参加したことが、研究者の道に進むことを決断させてくれましたね。
※大阪大学 ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラム:
情報科学研究科、生命機能研究科、基礎工学研究科の密接な連携により、他の領域の専門知識を獲得して自身の領域にフィードバックする双方向性を備えたネットワーキング型博士を生み出すためのプログラム。