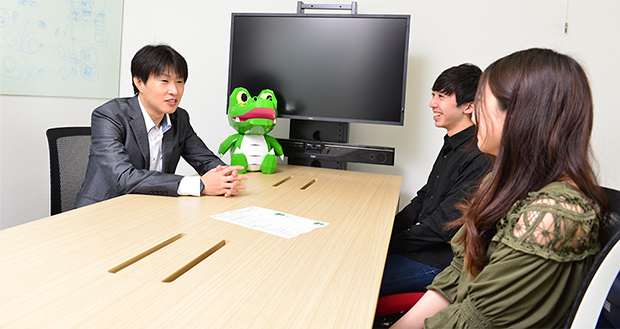コンピュータサイエンス専攻
ソフトウェア工学講座
教授
肥後 芳樹
Higo Yoshiki
研究内容について教えてください
ソフトウェア工学を研究しています。ソフトウェア工学というのは、品質の良いソフトウェアを効率的に、できるだけコストをかけずに作るための学問です。
たとえば身近なところだとスマホやパソコン、他にも様々な家電の中にもソフトウェアが入っています。社会での需要が大きい分野なので、それを効率的に作るのはとても重要なことです。
いま日本では「2025年の崖」ということが言われています。これは、現在IT人材が不足しており、このままだと社会の需要に対してソフトウェアの供給量がおいつかない状態になる、というものです。それは、毎年12兆円ほどの経済的な損失に繋がるとも予測されています。そうしたIT人材の不足による負の側面を和らげるために、ソフトウェアをなるべく効率的に作れるような技術を生み出そう、というのが私が研究している学問になります。
その中でも私が特に取り組んでいるのが、ソフトウェアのソースコードを対象にした研究です。
ソフトウェアの中でもバグが発生して人間が直さなければいけないところを、機械が自動的に直すことができれば人の手は少なくて済みます。ソフトウェアの自動プログラム修正、のようなことを研究しています。今では、1行や2行のバグであれば直すことができるようになってきています。
ソフトウェア工学の中でもホットトピックの一つで、GoogleやMSのような企業でも研究されているようです。


ここの研究室では学生を育ててくれる雰囲気がとてもあると思いますが、
先生として学生指導では何か工夫されていますか?
学生たちはみんな問題解決能力がとても高いので、僕は最初の課題を決めたら、詳細はあまり深く言わないんです。進捗は1週間に1回報告してもらうのですが、具体的な方法は彼らが自分で考えてやってくれます。なので僕はあまり研究手法や手順を詳しく指導しないようにしています。
最初の課題を立てる方法は、大きく分けて二つの柱があります。論文から見つけるか、共同研究で相手の企業が何を解決したいかを聞いて、課題を見つけるか。
論文には、やはり研究のトレンドのようなものがあるんですね。自動プログラム修正なら、最近どんな論文が発表されたかなどは把握しておいて、いまどんな研究が求められているかを把握・分析します。トレンドを把握しておかないと、次の研究テーマを決めるのは難しい。
研究テーマを決める手法のもう一つは、テーマそのものが社会のニーズに近いので、そういうところからのニーズをうまくくみ上げることですね。この研究室では、現在、共同研究を複数行っているのですが、それもニーズ志向型の研究になっていくと思います。
研究以外の指導では、ここ数年は対外的に国際会議で発表したり、論文を出したりするような、外部に向けて発信する取り組みを学生にも促すようになってきています。特に国際会議は、学生にとっても良い刺激になるかなと思っています。「英語で発表しよう」って言うと最初は大体「うっ」ってなるんですけど、まあためになるから、と説得して。学生のあいだにそういうことをやっておくと、社会に出る前に度胸がつくかなと思っています。
うちの研究生でいい流れができているなと思うのは、ここ数年はほぼすべての学生が海外で発表しているんですよね。そうした流れができているので、新しく配属された学生も、英語で発表するのは特別なことじゃなくて、みんながしている普通のことなんだと思ってくれているんじゃないかと思います。
卒論を書くときも、修士の学生から添削してもらうこともあるので、研究室内での縦のつながりもできますね。学生間で情報共有もしますし、先輩が後輩を自主的に面倒をみてくれていたりもしますし。そうした中で、英語で学会発表することや論文を出すことが普通のことになっていってくれれば嬉しいです。
コロナ禍の前までは、多い学生だと修士卒業するまでに3回は海外で発表していました。学部4年生から発表に行っているので、年に1回のペースです。
学生の時に取り組んだ研究の内容そのものが、就職して必ず活かせるかというと、そうではないことも多くあります。会社に入って違う仕事をする学生もいると思います。けれども学生の間に取り組んだ、研究に熱心に取り組む工程には、調べ物や発表や文章を書くといった作業が多い。そうした経験を通じて学生の能力が高まっていくと思うんです。この研究科で能力を高めてもらって、仕事に生かしてもらって活躍してもらう、というのがいい流れかなと思っています。研究の内容そのものはあまり役に立たないかもしれないけど、自分が熱意を持って取り組める研究をやるのがとても大事かなと思います。やっぱり努力より夢中になれることは大事ですから。