コンピュータサイエンス専攻
ソフトウェア工学講座
教授
肥後 芳樹
Higo Yoshiki
これから研究科を目指す学生に向けて、メッセージをお願いします
興味のある研究に取り組んでください。研究する過程が自分の能力の向上にむすびつくことを意識してほしいと思ってます。そうすれば研究生活を頑張る力になると思います。
自分の興味に従うというのは、すなわち、偏差値だけで選ばない、ということでもあります。夏休みなどのオープンキャンパスに行って、自分の志望する研究科や学部が自分と肌が合うか、相性がよさそうか、を見るのがいいかなと思います。ウェブページなどの人づての情報だけではなくて、実際に行ってみないとわからない感覚はあると思います。実際に足を運んで、その大学が自分に魅力的に映るかを調べてほしい。こういう研究がしたい、という強い気持ちがあれば志望動機につながると思うので、受験も頑張れると思います。大学に合格したあとでその研究室に所属することができれば、夢中になれる研究ができると思いますから、より、研究する過程で自分の能力を高めることができるのではないかなと思います。
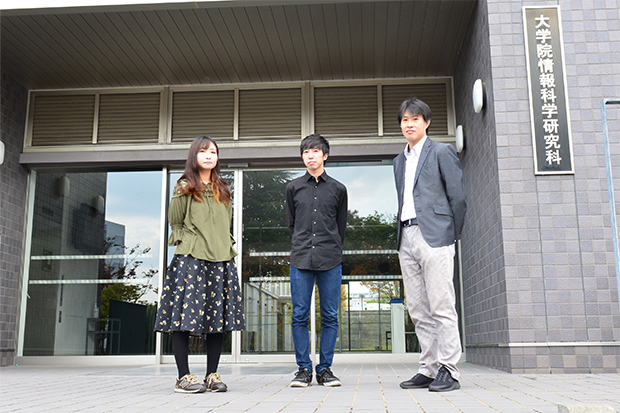
学生からのメッセージ
共同研究で大学外の人と一緒に研究をするのは、プレッシャーもありますが、しっかり取り組めば逆に自信にもなると思います。
個人でやるのとは勝手も違いますし、打ち合わせごとにここまで進みました、といった進捗を発表することが当たり前の雰囲気もあります。それは一人でやるよりはシビアなのですが、やる気は出ると思います。
僕はプログラミングをしたくてこの学部に入りましたが、プログラミング以外にもパスコン、スマホが好きな人は合うと思います。ただしこういう学科でも、最新技術を重点的に研究するのは案外少なく、昔からある理論や技術に触れることのほうが多いです。
僕も1年目、2年目のときはなんでこんなのをやるんだ?って思ってたんですけど、時間が経ってくると、そういう部分の知識が新しい研究の土台になっていると気付くようになります。
研究以外の部分でも、最新技術に触れる機会が増えてくるんですが、そうした部分の技術を理解するのにも役立ってきます。上澄みだけではない基礎から学べるし、研究でも底力がつきます。
高校生、大学生の頃は大学院での研究生活を具体的にイメージできずにいました。でも研究室に入ると皆が当然のように国際会議に行き英語で発表し、企業と共同研究しています。
全員が初めから全部できたわけじゃないです。肥後先生には、研究者だけど教育者でもある印象を多く感じています。私はここでの研究を通して英語が上達したし、論文も形にできるようになりました。
ここにいたら成長させてもらえる、育ててもらえる、という実感があります。いい研究室です。わたしは楠本研で間違いなかったと思うので、同じように思ってくれる人に入ってもらえたらと思います。








