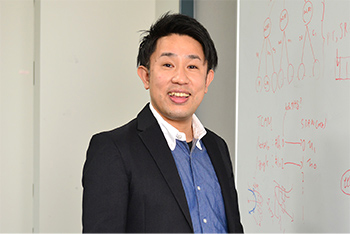情報ネットワーク学専攻
情報流通プラットフォーム講座
准教授
小泉 佑揮
Koizumi Yuki
小泉先生の教育研究活動に対する考え方を教えてください
アインシュタインの様々な格言が好きなのですが、教育についても好きな言葉があります。それは、「教育とは、学生たちが学校で学んだことを全て忘れた後に残るものである」というものです。授業は残念ながら、知識を教える以上のことは難しいので、知識を教えることに集中しています。それが将来の学生の研究の糧になれば良いという気持ちでいます。
一方、研究活動では、実際に研究しているトピックそのものを教えるに留まらず、物事の考え方や、研究を通してこのあと学生が人生を生きていくうえでの考え方を醸成するという役割があると思います。そうした役割の違いがあるので、研究のときと授業ではアプローチが違いますね。単に知識を植え付けるのではなく、学生が社会で生きていくうえでの考え方を身に着けてもらったり、経験をさせてあげたいと考えています。
大学における研究は、研究と教育のバランスを取るのが重要であり、そこが難しいと感じています。まず、研究において世界のトップにならないと、論文は出ません。誰かの後追いだと論文として評価されない、厳しい勝負の世界です。一方では研究は教育の過程でもあるので、学生がそれを通じて成長しなくてはいけない。そこのバランスにはいつも苦慮しています。
僕がテーマと研究行程までを全て明示して、全部これでついてきなさい、これをやりなさい、というのは間違っていると思いますし、テーマだけを与えて後は全部学生が自分でどうにかしなさい、というのも間違っていると思います。日々、最もふさわしい研究と教育のバランスを考えています。


大阪大学 大学院情報科学研究科の魅力は何だと思いますか?
世界レベルである、ということでしょうか。学生は気づいてないかもしれませんが、学生、特に博士前期課程のうちから国際会議に参加できる環境があります。学生は簡単に「この前どこの国際会議に出てきた」と言いますが、本当は簡単なことではないと思います。また、そうした場にも気負わずさらっと論文を書いて発表する学生が居ることも素晴らしいところだと思います。もちろん、他の大学でも国際会議に参加する学生は居るでしょうが、ここはその中でも世界第一線にも出られる学生が多いと思います。そうした学生を教育できる環境や設備が整っている、とてもいい環境だと思います。
情報科学研究科の教員は、普段の研究生活の中で、学生をどう巻き込むといい感じに国際会議の場に持っていけるか、というのを試行錯誤されていると思います。博士前期課程のうちから国際会議に参加していることは、教育と研究がいい感じでバランスよく動いている証左ではないでしょうか。学生が研究者の手足ではなく、その人なりに考えて、研究テーマに求められることもやってくれている、といういい例が多くあります。あとは、みんなこっそり他の研究室はライバルだと思っているんじゃないでしょうか。常に他の先生よりもいい会議に出したい、いい論文を出したいというように、研究科全体が、いい競争になっているんでしょうね。